Pick Up Hospital

NST・緩和ケアチーム・褥瘡委員会・訪問看護etc…さまざまなナースによるさまざまな看護のカタチを徹底レポート!
※掲載されているデータは取材当時のものです
Pick Up Hospital 20 [ 2013.9 ]
看護師としての道を着実に歩んで欲しい。
その支えの一つである「お助け塾」とは?
地域の急性期医療から在宅医療までを担う中核病院である茨城西南医療センター病院では、医療・看護現場において新人看護師にも期待がかかる。しかし、その中で職場に適応できず離職を考える新人看護師がいることも現実である。入職後間もない時期、新人看護師にとって一番緊張し、ストレスが高いこの時期に不安や悩みを軽減することはできないか? その方法として、職場を離れ、同期と交流することのできる「お助け塾」が考案された。今回はその「お助け塾」について看護部副部長の高谷智子さんと、実際に「お助け塾」に参加した看護師の額賀恵理奈さんにお話を伺った。
茨城西南医療センター病院

▲病院外観
〒306-0433 茨城県猿島郡境町2190
TEL:0280-87-8111(代)
URL:
http://www.seinan-mch.or.jp/
■開設年/昭和21(1946)年
■開設者/茨城県厚生農業協同組合連合会
■院長/亀﨑髙夫
■看護部長/宮本留美子
■病床数/358床(一般356床、感染床2床)
■職員数/665名(看護職315名)
■診療科目/内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、神経内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、小児科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、救急科
■指定機関/救命救急センター(第三次救急医療)、地域周産期母子医療センター指定、地域がん診療連携拠点病院
■看護配置/実質配置 7:1
■外来患者数/1,014名(1日平均)
■入院患者数/274名(1日平均)
■附属施設/茨城西南医療センター病院附属八千代診療所
■関連施設/土浦協同病院、JAとりで総合医療センター、なめがた地域総合病院、水戸協同病院、県北医療センター高萩協同病院
■敷地面積/16,122.25㎡
■建築面積/27,050.89㎡
■交通案内/東武伊勢崎線『東武動物公園駅』より朝日バス車庫行き『西南医療センター病院入口』下車、徒歩3分、JR宇都宮線『古河駅』西口より朝日バス境車庫行き『西南医療センター病院入口』下車、徒歩3分
新人看護師の悩みは何か? どうすればストレスや
悩みを解消できるか? 「お助け塾」の役割とは?

- 看護部副部長
高谷智子

- 看護師 額賀恵理奈
2013年4月入職
脳神経外科病棟勤務
土浦協同病院附属看護専門学校卒

「お助け塾」の発足意図と開始までの経緯をお聞かせください。
(Median編集部)
- 高谷

高谷副看護部長
当院の看護部では、数年前からプリセプター制度を導入し、新人看護師の教育を行っています。しかし、数年前までは毎年数名の新人看護師が1年以内に離職していくという現実がありました。看護師の仕事のやりがいも素晴らしさも知らずに辞めていくのは残念なことです。そこで1年以内の新人看護師がどのような悩みを持ち、また誰に相談をしているのか、といったことを新卒看護職12名にアンケートを実施しました。結果、6名が先輩看護師との人間関係に悩んだ、と答えていました。悩みをその後解決できなかった者は2名で、同僚や他の施設の人に相談していると答えていました。このような結果を踏まえて、同僚との交流を深めることが、入職から配属部署の人たちに慣れるためには必要なのではないか、と考えたわけです。
平成23年4月から検討に入り、目的を『新卒看護師が入職後、リアリティショックを乗り越え職場に適応することができる、入職間もない時期にかかえる悩み・不安を表出することができる、同期入職との交流を深める場の提供をする』としました。時期と時間は、4〜6月の毎週金曜日、16:00〜17:00の1時間のうち、30分の講義と30分の情報交換で構成し、実施に至りました。

リアリティショック、病棟での人間関係など新人看護師が陥りやすいできごとで、特に最近の傾向として感じられることなどはありますか?
- 高谷

入職して3ヵ月で適応障害が出てしまう方もいました。不眠や食欲不振、病院に来ると下痢をする、体重減少、などを引き起こし、自分は看護師に向いていないと思ってしまう。「病院を辞めたい」や他の施設や病院に就職した友達から情報を得て、他の所の方が当院よりも楽なイメージを持ち、「そちらに移りたい」と思ってしまいます。
特に学生時代に成績の良かった人や、他の人から頼られていた人にありがちな傾向です。学生の時とのギャップを感じ、同期と比べてしまったり、できない自分が受け入れられなかったりするのでしょう。他には社会人経験がある人もプリセプターが年下だったり、周囲は自分のことをもっとできる人として見ていることがプレッシャーになったりするようです。いわゆる真面目で、責任感の強いタイプです。
1つの目安として、所属の職場に慣れたかどうかは、そこの休憩室で休憩や食事がとれるかどうかで判断できます。いつまでも地下の食堂や自分の車の中で休憩していた人が、部署の休憩室で休憩がとれるようになったら大丈夫です。また、マスクをして手放さない人も要注意です。必要のない時のマスクは自己防衛の表れです。職場に慣れてくると自然とマスクをしなくなります(笑)。

お助け塾のプログラム内容を立案される際に留意された点はどのようなことでしょうか?
- 高谷

第1回 お助け塾
まず、勤務時間内に実施することです。あえて時間内に、ということに意味があります。新人看護師が「お助け塾」に行くことに周りのスタッフが協力して、「行ってらっしゃい」と送り出してほしかったのです。先輩を含めみんなで育てていくことが大事だと考えました。
「お助け塾」で話した内容は、その場限りとし、特に重要だと思われることは看護部へ伝えることを、参加者に伝えました。時間外の記入方法が分からない、年休の書き方が分からない、先輩の話している内容が分からない、などといった内容が出てきたのですが、こちらの予想外のことで悩んでいることが分かりました。それらを現場にフィードバックして、現場でも気づいてもらうことが必要です。

第1回に開催されたコラージュとは、心理療法としてのコラージュ療法に近いものなのでしょうか? この方法を取り上げた背景と、当日の参加者の反応について聞かせてください。
- 高谷

コラージュ制作の様子
私が産業カウンセラーの資格を持っていてそこで学習したことと、新人看護教育担当者研修会に参加した時に、他の病院で取り入れている話を聞いてきたことがきっかけとなりました。
平成23年には、はがき大の用紙に各自で絵を描いてもらいましたが、絵が苦手な人もいたため、平成24年は、コラージュを取り入れてみました。最初は戸惑っていた参加者もだんだん楽しんで取り組んでいたようです。現在の自分の心境ということで、ファッション雑誌を切りぬき、吹き出しをつけたり、絵文字を入れたりと自分なりの発想で作成し、楽しい回になったと感じています。
コラージュを作成することで、現在の心境や心の状態などを判断し、対応するようにしています。「心配だな」と気になる看護師がいたら、その場で声をかけ、話を聞いて、相談にのるようにしています。
中には暗い絵を描く看護師もいます。配色が1色だったり、涙の絵を描いたり……。そういった看護師に対しては、部署と情報を共有し、丁寧にフォローしていきます。

実際に実施してみて、いかがでしたでしょうか?
- 高谷
-
実施後のアンケートを集計してみると、半数以上が『とても良かった』と答えてくれています。『心が救われた』といった言葉を聞くと、やって良かったと思います。
ただ、特別なことをしているとは思っていません。入職して3ヵ月もしないで辞めたいと思ってしまう新人看護師に対して自分のできることは何か?を考えて実施したのが「お助け塾」です。
5月末くらいの時期に新人看護師はどのような心境でいて、どのような思いを持って仕事をしているのか、その時に必要なことは何か、について理解することができ、そして対策を立てることができる、という体制はとても重要だと感じました。開催した年は、その後結婚退職はありましたが、他の理由によって辞めた新人看護師はいなかったと聞いています。本当に実施して良かったです。

新人看護師が病棟に帰ってからどのように活かせているかなど、病棟での活用はいかがでしたでしょうか?
- 高谷

病棟ではプリセプターがフォロー
前半の学習面においては、点滴の計算をもう一度学習できた、基礎看護技術は、理解しているようで分かっていない点もあり、今回理解できて良かった、という声が寄せられました。また、情報交換の場面では、コミュニケーションの場になった、職場で悩みがあった時に役に立った、という声もありました。出身学校から一人で入職している看護師もいますから、その後仲間同士で声を掛け合っているようです。お助け塾が交流のきっかけとなり、さまざまな話をしたり、聞いたりすることが、職場での支えになれば嬉しいですね。

来年に向けての課題を聞かせてください。
- 高谷

研修後の一コマ
平成23・24年は1週間に1回実施したのですが、業務中に抜けてくるのが大変という意見があり、25年は2週間に1回とし、開催時期を6月まで延長しました。
また、担当を看護部(高谷)から、新人教育委員会へ移行しました。その際に、当初の「お助け塾」開催の意図と目的を伝えたつもりだったのですが、学習がメインとなってしまい、情報交換の時間がとれなかった、という回もありました。さらに委員会主催となり、担当者が複数になって、役割をそれぞれが真面目に遂行するため、リラックスした雰囲気をうまく演出できませんでした。
来年はもう一度初心に戻り、情報交換をメインに進行できるよう、委員会メンバーと検討していきたいです。「お助け塾」が終了した後、1年間を通してフォローできるような体制作りを考えていきたいと思っています。現在は、個人面接を通してメンタルヘルスをフォローしています。

最後に、新人看護師の育成にあたって、注意点、期待する成長後の姿などを聞かせてください。
- 高谷

仕事風景
新人看護師を「即戦力」として考えずにすむような環境作りをしていきたいですね。急性期医療を担う病院としては、新人看護師に多くを求めてしまう、さまざまなことを詰め込みすぎてしまう、ということは仕方のないことでもあるのですが、新人看護師ではなく、1人の看護師として人格を認め、育成していけるような職場風土を作っていきたいです。
自立した看護師に向けて、何がしたいのか目標を持った看護師になってもらいたい。看護の仕事は楽しいばかりではありませんが、楽しんで欲しい。そのためには、上手に息抜きをしながらワークライフバランスを考えて、公私ともに充実した日々を送って欲しいです。帰属意識を持ち、組織の一員として患者さんの安全・安心のために、日々、成長して欲しいです。
実際「お助け塾」を体験した看護師・額賀恵理奈さんに
お話を伺いました。
「お助け塾」に参加されて、印象に残っていることは?
- 額賀

看護師 額賀恵理奈さん
入職して3ヵ月経った頃に参加した「お助け塾」で、それまでの自分の仕事を振り返る機会がありました。KJ法を使って、できたこと、できなかったことをまとめたことが良かったです。日頃は全然できていないと自分では思っていたのですが、できたことを並べてみると「こんなにたくさんのことができるようになっていたんだ!」と、少し感動しました。

病棟の雰囲気はどのような感じですか?
- 額賀

いつも見守ってくれるプリセプター
「お助け塾」に参加する際、病棟の先輩方は「仕事はいいから、遅れないように出かけて」と好意的に送り出してくれました。そういった先輩たちの優しさがあり、気軽に参加することができたのは、うれしかったです。

「お助け塾」に参加された感想を聞かせてください。
- 額賀

入職して不安がいっぱいだった時に参加できたので、本当に助けられました。自分の看護を振り返り、小さなことでも、少しだけでも、こんな自分でもできるようになった、と実感することができました。部署が違う同期に会って、いろいろな話を聞いて、不安なのは自分だけではない、これで良かったんだ、と自信を取り戻すとてもいい機会になりました。
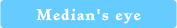
地域の中核病院としての役割を担う茨城西南医療センター病院においては、新人看護師に求められるもの、期待されることが大きい。その期待に応えたいというプレッシャーも小さくはない。予想以上にできない自分に自信を失い、感じる必要のない劣等感に悩む看護師たち。入職したばかりで相談できる相手も、話を聞いてもらえる相手も探せずにいる。そんな新人看護師たちに手を差し伸べるのが「お助け塾」である。
誰にも気兼ねなく話をすることができ、思ったことを言葉にできる場、同じ目標を持ち、同じ悩みを持つ仲間がいることを実感させてくれる「お助け塾」。さらに、参加した看護師たちの本当の気持ちを理解し、言葉では言えない、本人でさえも気づいていないサインを感じ取り、救ってくれる。看護師としての大切なスタート地点にある「お助け塾」が、輝ける未来に手を伸ばす看護師たちの心の支えになっていることは、間違いない。そんな細かなフォローアップが実を結び、看護の質の向上へと繋がっていると感じた。


















![]()