Pick Up Hospital

NST・緩和ケアチーム・褥瘡委員会・訪問看護etc…さまざまなナースによるさまざまな看護のカタチを徹底レポート!
※掲載されているデータは取材当時のものです
Pick Up Hospital 8 [ 2010.4 ]
ケアをするなら、手技の不安を一掃してから!
患者さんのため、徹底的に手技をマスター。
ストーマの造設やCAPD(腹膜透析)の導入をしている患者さんは、ボディ・イメージの変化が大きく、ナースは手技を習得して日常的にケアする必要があります。患者さんが一変した生活を受け入れられるように行われている、セコメディック病院の3B(外科・泌尿器科)病棟の患者指導に注目してみます。
医療法人社団誠馨会 セコメディック病院
〒274-0053 千葉県船橋市豊富町696-1
TEL:047-457-9900(代) 担当/総務課
■開 設 年/1998年12月1日
■病 院 長/景山 雄介
■看護部長/小池 文江
■病 床 数/292床(一般:246床、回復リハ:39床、ICU:7床)
■職 員 数/502名
■診療科目/内科、外科、小児科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、糖尿病・代謝・内分泌内科、脳神経外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻いんこう科、皮膚科、形成外科、眼科、歯科口腔外科、放射線科、リハビリテーション科、神経科、心療内科、心臓血管外科
■看護配置/実質配置 10 : 1
■併 設/訪問看護ステーション
■認定看護師/皮膚・排泄ケア認定看護師1名
■施設認定/日本医療機能評価機構認定病院
■交通案内/東武野田線『鎌ヶ谷』駅、新京成線『高根公団』駅、北総線『小室』・『白井』・『千葉ニュータウン中央』駅、東葉高速鉄道『八千代緑が丘』・『村上』駅より無料送迎バスあり
ストーマ、CAPD(腹膜透析)における患者指導の独自の取り組みとは?

- 看護師長
伊東 都さん

- 皮膚・排泄ケア認定看護師 小俣佳子さん

ストーマを造設した患者さんのために使用しているパンフレットはどのようなものなのか教えてください。(Median編集部)
- 伊東

看護師長の伊東 都さん
ストーマには泌尿器系のものと消化器系のものがあり、それぞれ排泄物が違います。さらに消化器系のものは、造設する場所によって排泄物の形状も違います。ケアそのものは変わりませんが、造設した場所、形や大きさ、患者さんやご家族の個性などにより、ケアには多少の違いが出てきます。その個別性に対応するため、内容や載せる写真の取捨選択をしたり、パンフレットの文字の大きさを変えるなどしています。作るのはプライマリーナースで、パソコンに入っているベースのデータを変更していきます。パンフレットというものは、その時に必要でも、状況が変化したり知識を習得してしまえば不必要になります。その必要な時に活用できなければ意味がないので、患者さん一人ひとりに合ったパンフレットというのは、とても価値があるものです。
- 小俣
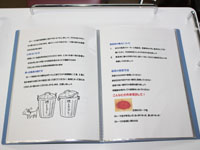
個別性に合わせて作成できる
パンフレット
パンフレットは私を入れて4名のナースが協力し、2年近くかかって作ったのですが、患者さん用だけではなく、ナース用も作りました。ストーマ造設が決まった患者さんへの精神的ケアや、造設手術前のオリエンテーションが徹底されていなかったり、ストーマに関する技術の統一ができていなかったので、まずそこを改善するためにチェックリストなどを盛り込んだパンフレットを作ったんです。その甲斐あってナース間に知識・技術が浸透し、より丁寧なケアに繋げることができるようになりました。患者さん用のパンフレットは、造設部分の写真はその患者さんの了解を得て撮影し、ご本人のものを載せています。それにより、患者さんから「退院後の見直しにも役立った」という声が聞かれます。また、「パンフレットを他の人に見せた時、『こんなにわかりやすく作ってもらえていいね』と言われた」と嬉しそうに報告してくれる患者さんもいます。
- 伊東
-
現在、パンフレットの追加事項として「新しい問題が発生したり困った時にはどこに相談したらいいか」ということの掲載も検討しています。そして実際、相談窓口を開設することが決まっています。
- 小俣
-
その相談窓口には私も入りますが、何かあった時に「認定看護師がいるから何でも相談できる」と思ってもらえることが、患者さんへの安心に繋がると思います。どこの誰に相談していいかわからないという状態だったら、患者さんも不安になってしまいますから。

相談窓口ができることで、患者さんの不安がさらに軽減されますね。では次に、CAPD(腹膜透析)の患者さんへの指導はどのように行っているのですか?
- 伊東

手技をマスターするために
練習を繰り返す
ナースの手技がバラバラだと患者さんが混乱し、不信感をもたれてしまうので、まずはナースの手技を統一することが必要になります。新人ナースにとって、実習などで経験しないCAPDの手技はまさに未知のものです。また、ある程度経験を積んでいるナースにとっても新たな勉強が必要になり、敬遠されがちです。だからといって「私はできないから他の人に頼もう」というわけにはいきません。CAPDには3種類あるので、それぞれ資料やDVDで勉強し、チェックリストを確認しながら習得に励みます。手技ができるようになったら透析室のコーディネーターのテストを受け、合格すると患者さんへのケアや指導ができます。マンツーマンで手技をチェックされるこの時間は、とても緊張するんですよ(笑)。1回で合格する人はほとんどいません。みんな3回目ぐらいでやっと合格します。それも3種類全部に合格しなければならないので、みんな苦労しています。ここを通過しなければ遅番も夜勤もできないわけですから、みんな必死です。ただ、全部に合格していなくても、合格しているものがあれば、それに関する患者さんには携わることができます。
- 小俣

チェックリストで手技を確認
患者さんへの指導では、コーディネーターとの連携が不可欠です。退院後に患者さんが日常的にケアできるよう、コーディネーターが患者さんへの指導を行い、手技をきちんとできるかどうかをナースが確認します。そしてできていない部分を重点的に指導します。退院を見据えていることもあり、患者さんには日常生活でのさまざまな不安や疑問が湧いてきます。質問されることもたくさんありますが、ナースが判断できないこともあるので、そのような時にはコーディネーターから説明してもらいます。これはナースにとっても心強いことですし、何より患者さんの不安を軽減できるというメリットがあります。
- 伊東
- 患者さんの年齢は、30?70代と幅広いのですが、高齢になればなるほど、手技をマスターするのが難しくなりますね。カテーテルなどの細かい部品に触れる作業が不可欠なのですが、触れてはいけない部分に触れてしまったり、目が悪くて目盛りが読めなかったりするので、やはり時間がかかります。

ナースにとっても患者さんにとっても、CAPDの手技をマスターするのは大変なんですね。次に小俣さんにお聞きしたいのですが、皮膚・排泄ケア認定看護師として、院内外でどのような取り組みを行っているのですか?
- 小俣

皮膚・排泄ケア認定看護師の
小俣佳子さん
院内では月1回1時間、4年目以上のナースにスキンケア関連の研修を行っています。診療科にかかわらず全病棟から10?15人ほどの出席があります。ここでは症例などをあげ、ナースとして関わるであろう皮膚の知識全般について話しています。院外では2ヵ月に1回、他院の褥瘡回診に参加し、アドバイスなどをしています。他院を見ることは、とても新鮮なんです。ケアの基本は変わりませんが、ベッドやマットなど使用しているものが当院とは違うので、褥瘡のでき方なども変わってきます。なのでガラッと視点を変えてアドバイスする必要がありますね。逆にその病院からしてみれば当院での取り組みが新鮮に映るようで、質問攻めにあったりします(笑)。その他にも、東関東、千葉県、船橋市など地域で行われる研修会で講師をしています。いずれにしても、ただ話すだけではなく、どのようにしたら参加者に興味をもってもらえるかを常に考え、参加者を巻き込んだ対話形式の講義にすることを心がけています。

患者さんのケアや指導にあたり、ナース自身が知識や技術を確実に身につけていなければならない、という意識が徹底していますね。
- 伊東

スタッフの連携が患者さんの
苦痛を軽減する
そうですね。「どうすることが患者さんのためになるのか」「患者さんはどうしたいのか」ということを日々考え、スタッフ間でディスカッションしています。肉体的にも精神的にも、患者さんの苦痛を最小限にとどめられるようなケアをすることが大切なので、常にそこを意識しています。当たり前のことですが、患者さんに敬意を払えるナースでいたいですね。
- 小俣

患者さんからの言葉がスタッフの
励みになる
以前、ストーマを造設した事実をなかなか受け入れられない患者さんがいました。でも、退院する時に「認定看護師の小俣さんがいてくれて心強かった」「何でも相談できるから安心だ」と言ってくれたんです。その時は、患者さんのためのケアがきちんとできたのかな、と嬉しくなりました。精神的ダメージが大きい患者さんだったからこそ、余計に嬉しかったんです。さらに患者さんから頼りにされるようなナースを目指し、院内外での活動にも力を入れたいと思います。
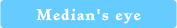
ストーマの造設やCAPDを導入することにより身体的変化が生じ、日常生活が制約されてしまう。これは肉体的にも精神的にもつらい状態だが、そんな患者さんの苦痛をどのようにしたら軽減できるか試行錯誤し、スタッフ一丸となって力を注いでいる病棟の姿勢からは、患者さん第一主義にいかに重きを置いているかが伝わってきた。






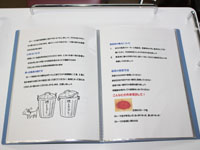





![]()