Pick Up Hospital

NST・緩和ケアチーム・褥瘡委員会・訪問看護etc…さまざまなナースによるさまざまな看護のカタチを徹底レポート!
※掲載されているデータは取材当時のものです
Pick Up Hospital 14 [ 2012.2 ]
食べ物を口から摂取する。
その可能性を見失わず、実現させていく摂食嚥下療法部の取り組み。
神奈川県厚木市に位置する東名厚木病院。地域の人たちが365日24時間、いつでも安心して医療が受けられること、という思いは現在まで引き継がれ、地域の急性期病院として地域の住民から信頼され続けています。さらには、法人内施設のクリニック、老人保健施設、訪問看護ステーション、透析センター、健診センターと連携し、保健・医療・介護・福祉に対するニーズにも応える医療をトータルに展開。地域医療支援病院にも認定され、地域住民の必要とする医療を常に把握しながら進化しています。
そんな中、小山さんが摂食・嚥下リハビリテーションの取り組みに着手し、土台づくりを始めたのが6年前。急性期医療における早期経口摂取を実現させてきました。現在では摂食嚥下療法部として医師、看護師、歯科衛生士、言語聴覚士、看護助手といった多職種によるチーム編成がなされ、摂食・嚥下リハビリテーションに関する積極的な活動を続けています。摂食・嚥下リハビリテーションへの取り組みをはじめ、その意義、思い、今後の展望などについて、摂食嚥下療法部 課長の小山珠美さん、同じく主任の芳村直美さんにお話を伺いました。
社会医療法人社団 三思会 東名厚木病院

▲外観写真
〒243-8571 神奈川県厚木市船子232
TEL:046-229-1771(代)
URL:
http://www.tomei.or.jp
E-mail:
suzuki@tomei.or.jp
■開 設 年/1981年
■開 設 者/社会医療法人社団 三思会
■院 長/杉山 茂樹
■看護部長/伊藤 玲子
■病 床 数/267床
■職 員 数/420名
■看護職員数/220名
■診療科目/内科、循環器科、消化器科、呼吸器科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、麻酔科、婦人科、リハビリテーション科、アレルギー科、リウマチ科
■看護配置/実質配置 7:1
■クリニック患者/700名(1日平均)
■入院患者/200名(1日平均)
■指定機関/地域医療支援病院、臨床研修指定病院、日本医療機能評価機構認定施設
■関連施設/とうめい厚木クリニック、介護老人保健施設さつきの里あつぎ、訪問看護ステーションさつき・もみじ、厚木市南毛利地域包括支援センター、居宅介護支援センター、総合健診センター、人工透析センター、社会福祉法人特別養護老人ホーム「はなの家とむろ」
■交通案内/小田急線『本厚木』駅または『愛甲石田』駅下車、『本厚木』駅より送迎バスあり

▲急性期医療
▲摂食嚥下療法部の回診風景
▲人工呼吸器装着の患者さんの食事風景
口から食べる基本的な行為の復活のため努力を続ける摂食嚥下療法部。

- 摂食嚥下療法部 課長
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会(認定士・評議員)
小山珠美さん

- 摂食嚥下療法部 主任(看護部教育担当兼任)芳村直美さん

小山さんが、摂食嚥下療法に携わるようになったきっかけは何だったのですか?(Median編集部)
- 小山

摂食嚥下療法部 課長 小山珠美さん
人が口から食べるという行為は、生きていくうえでとても大切なことです。栄養摂取は点滴などからでもできますが、食べ物を見て、感じて、味わうということは、人間の脳を刺激し、体を動かし、元気になっていくことにつながるのです。しかし、急性期医療での在院日数の短縮化、人手不足、スキル不足などの問題で、経口摂取が可能であるのに、口から食べることを禁止している現実を多く見聞きしてきました。その現実をなんとか変えて、早期に口から食べることができるようなリハビリテーション看護をしたいと切望したからです。
ここは急性期の病院ですから、入院と同時に治療が始まります。患者さんにはその時から摂食・嚥下リハビリテーションを始める必要があります。もちろん、患者さんの状態によってはできることとできないことがありますが、それさえも判断せずに、経口摂取の機会を失くしてしまい、口から食べ物を食べられなくしてしまうのは医療者側の責任が大きいと思います。

そこで摂食嚥下療法部の役割が重要になるのですね。摂食嚥下療法部の具体的な活動内容を教えてください。
- 小山

急性期におけるアプローチ(介入)
急性期医療においては入院と同時に治療と平行して、摂食・嚥下リハビリテーションのアプローチをします。全身状態はどうか、意識レベルはどうか、気道クリアランスはどうか、嚥下機能はどうか、などを確認し、経口摂取の可能性がどれくらいあるかを評価します。その評価をもとに、その患者さんに応じた食形態や摂食・嚥下リハビリテーションの環境づくりをしていきます。
また、高齢になると食べる力や飲み込む力も低下します。誤嚥が起こり、誤嚥性肺炎になってしまったりすることもあります。しかし、誤嚥を怖がって絶食にしていては、口から物を食べる可能性を奪ってしまうことにもなります。そうさせないために、私たちが適切な評価をします。院内では、摂食嚥下療法部に評価の依頼が来て、入院後すぐに患者さんの身体状態や口腔状態などの環境整備をし、評価をしていきます。

摂食・嚥下の評価は、具体的にはどのような方法で行うのですか?
- 小山

環境調整や姿勢のポジショニング、
トレーニング
全身状態の確認から問診、視診、触診、聴診、反復唾液嚥下テスト、改定水飲みテスト、フードテストを行い摂食・嚥下機能を評価します。例えば、脳血管障害などの患者さんで、意識障害があったとしても、その程度によっては、医師と相談したうえで、最初は食べられるゼリーから、摂食・嚥下リハビリテーションのアプローチをしていきます。
アプローチの方法としては、ゼリーなど食形態の調整ももちろん大事ですが、口の周りのトレーニングや姿勢調整を行い、スムーズな口腔ケア、嚥下運動ができるようになる環境整備がとても大切です。

摂食嚥下療法部の存在は大きいですね。摂食嚥下療法部のチーム編成はどのようになっているのですか?
- 小山

摂食嚥下療法部ミーティング
医師、歯科衛生士、パート看護師、看護助手がそれぞれ1名、言語聴覚士が2名、専従の看護師が4名で活動しています。現在は1日40名程度の患者さんの介入を行っています。毎日1人ひとりの食事や状態を確認し、アセスメントを繰り返し、患者さんの食事のステップアップやモニタリングを行います。
最初は私1人でしたから、いろいろと大変なことが多くありました。摂食・嚥下リハビリテーションに必要な食品や物品、設備も足りなくて……。今ではゼリーの種類も増え、スプーンなどの物品も充実してきました。テーブルや枕、イスなどの備品も徐々にそろってきています。さらに優秀なスタッフが育ち、摂食・嚥下リハビリテーションを実践できるようになり、その結果、口から食べられるようになる患者さんが少しずつ増えてきています。

病院でアプローチできる時間は限られていると思うのですが、退院後のケアについてはどのような取り組みが行われていますか?
- 小山

嚥下造影結果から食事介助方法を
アドバイス
せっかく病院で口から食べられるようになったのに、自宅に戻ったら口から物を食べられなくなってしまう患者さんも、残念ながらいらっしゃいます。どうしても、家族の方は誤嚥を心配してしまうのですね。
退院指導としては、ご家族の意向を踏まえて、当院の退院調整専従看護師とサービス調整を行います。ご家族がどこまでできるかを確認し、誰がどのくらい時間をかけてケアができるか、できない場合はヘルパーなど福祉サービスについてもアドバイスをします。在宅でのケアについては、食事の介助の仕方や食品の扱い方などについても、実際の食事場面で細かくアドバイスします。何よりも、ご家族の患者さんに寄せる願いや頑張りを大事にしたうえで、サービス提供者のサポート体制が整うような退院調整が必要だと思っています。

摂食嚥下療法部の担う役割とは?
- 小山

他職種との検討風景
物を食べる行為は脳の指令によって行われます。食べ物を見る、右手を動かす、口に運ぶ、こぼさないようにするにはこのくらいの量を口に入れる…などすべて脳が指令を出します。脳が働くということは、手足など体を動かすことになり、身体的機能の向上にもつながるのです。私たちの役目は、そのチャンスを逃さないこと。急性期に入院した患者さんの口から物を食べられるという可能性をつぶさないことです。
病院や施設によっては摂食・嚥下リハビリテーションに対してそこまで力を入れられないという現状があります。しかし、ADLを向上させ、患者さんを元の生活に戻してあげたい、という思いは共通のはずです。そのためにも、私たちは摂食・嚥下リハビリテーションの取り組みを記録し、伝えていくことを続けていく必要があります。ありがたいことに、こういった取り組みに賛同してくれるスタッフがしっかりと育ってくれています。その1人が主任として活躍している芳村です。

摂食嚥下療法部は本を出版するなど、活動内容は院内だけに留まりません。摂食嚥下療法部のスタッフで、小山さんの活動に賛同し、現在、摂食嚥下療法部 主任として活躍されている芳村さん。こちらで活動するきっかけは何だったのですか?
- 芳村

摂食嚥下療法部 主任 芳村直美さん
摂食・嚥下リハビリテーションに対する小山さんの考え、取り組み、全てに感銘を受けたからです。小山さんが持つ知識や技術、全てを自分のものにしたい、という思いで一杯でした。だから、最初は金魚のフン状態。ずっと小山さんにくっついて勉強しました。小山さん自身が、OJTをとても大切にする人ですから、現場で小山さんのやり方、行動などをしっかりと目に焼き付け、自分の力へと変えていきたいと思いました。
また、『今日できたことは、明日はもっとよくできる』『今日できなかったことは、明日できるかもしれない』と言う小山さん。こういった可能性に挑む信念があるからこそ、成果が生まれるのだと感じています。

小山さんから受け継いだもので、現在のケアに生かされていることは何ですか?
- 芳村

家族などへの退院指導
口から食べるということは、患者さんの生きる意欲も高めるということです。私たちは口から食べられる可能性を見つけ、それをステップアップさせていきます。さらに病院でステップアップさせたことを、在宅や施設でも継続していく必要があります。そのための家族への指導はとても重要です。そこで大切にしているのが、実際に目で見て、一緒に行いながら学んでもらうこと。人と人とが顔を合わせて、その場で実際にはどのように行うのかを、体感してもらうようにしています。口腔ケアや、姿勢、介助方法など共有することで、患者さんが退院後も食べつづけていける環境が整うのだと考えるからです。食支援は命のリレーだと思いますし、私たちは命のバトンをしっかりと次へ渡す役割を担っていると思います。
摂食嚥下療法部としての今後の目標を聞かせてください。
- 芳村

「早期経口摂取実現とQOLのための
摂食・嚥下リハビリテーション」
多職種で編成された摂食嚥下療法部は、さらなる活動し摂食・嚥下リハビリテーションの質の向上に努めています。しかし、私たちだけの力では、全ての患者さんに対する取り組みを行うことはできません。院内はもとより、他施設においても同等の取り組みが行われなければなりません。そのためにも、本の出版やセミナーなどを開催し、摂食・嚥下リハビリテーションの早期取り組みの重要性、あきらめずに根気強くかかわる具体的アプローチなどを伝えることが必要です。さらにFACE TO FACEの顔の見える関係で地域との連携を強め、ネットワークづくりに尽力したいと考えています。
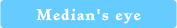
ほとんどが胃瘻栄養のみだった80歳代の患者さんが「牛丼を食べたい」と入院されたそうです。入院による摂食・嚥下リハビリテーションの結果、なんと9日間で全面経口へ移行でき願いが叶ったそうです。可能性があるなら希望を失わず、諦めず、チャレンジしていく。その思いや取り組みは、患者さんやその家族にも希望を与えてくれます。口から食べるのは不可能だ、と思われていた患者さんに対しても、アプローチを続けることで食べられるようになった、という実績を確実に増やしている摂食嚥下療法部。しかし、それが全ての人に受け入れられているわけではないと小山さんは言います。それでも、患者さんを少しでも以前の生活に戻すために、常に努力し続けているスタッフの皆さん。「今日はこれも食べられるようになったよ」と言ってくれる患者さんや家族の笑顔が、その原動力になっているに違いありません。

















![]()