Pick Up Hospital

NST・緩和ケアチーム・褥瘡委員会・訪問看護etc…さまざまなナースによるさまざまな看護のカタチを徹底レポート!
※掲載されているデータは取材当時のものです
Pick Up Hospital 1 [ 2008.10 ]
笑って学ぶ、職員のための教育・研修活動。
設立当初より地域社会との交流を大切にし、保健・医療・福祉活動を包括的に提供する全人的医療を追求してきた京都南病院。柔軟で開かれた病院づくりをめざす同院らしく、職員の教育・研修方法にも工夫を凝らしています。今回は、そんな同院のオリジナリティ溢れる教育・研修活動『院内劇場』について注目してみました。
特定医療法人健康会総合病院 京都南病院
〒600-8876 京都市下京区西七条南中野町8
TEL:075-312-7361(代)
E-mail:
soumu@kyotominami.or.jp
■開 設 年/昭和28年
■理事長・病院長/清水 聡 看護部長/寺口淳子
■病 床 数/306床
■職 員 数/480名
■診療科目/内科、外科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科、婦人科、泌尿器科、脳神経外科、麻酔科、形成外科、神経内科、心療内科、アレルギー科、
リウマチ科、リハビリテーション科、消化器科、呼吸器科、循環器科、肛門科、放射線科、精神科専門外来/糖尿病、アレルギー、血液、脳疾患リハビリ、高脂血症、健康管理、予防接種、乳腺外科、手の外科
■看護配置/実質配置 10 : 1
■外来患者/約500名(1日平均)
■入院患者/約250名
■医療施設/人工透折、シネアンギオ、DSA、マンモグラフィー、全身用CT、MRI、超音波診断装置、手術室 (クリーンルームクラス100)、理学療法訓練室、作業療法訓練室ほか
■交通案内/JR「京都駅」より市バス208、33、205系統にて10分、阪急電鉄「西院駅」より市バス205系統にて5分、ともに「七条御前通」下車すぐ
■関連施設/分院診療所6ヵ所、老人保健施設“ぬくもりの里”、訪問看護ステーション、在宅介護支援センター、グループホーム“ぬくもりの里”、ヘルパーステーション“みなみ”

▲第二南診療所
▲内浜診療所
▲西京極診療所
▲せんぼん診療所 他
“役者ナース”に聞く!院内劇場とは?

貴院の院内劇場は、職員の教育・研修の一環として2001年から行われているそうですが、劇団発足の背景や経緯についてお聞かせください。(Median編集部)
- 寺口

演劇、イラスト、ダンスなど多彩な
特技をもつ寺口淳子 看護部長
たとえばリスクマネジメントについて1時間の研修時間があるとして、1時間ずっと講義をするのもいいけれど、もっと印象に残る伝え方はないかと以前から考えていました。そこで、特に大切なポイントや、患者さんの退院アンケートなどを事例にテーマを抽出し、それを劇仕立てにしてはどうかという意見が出たんです。そういうことなら、と、高校時代から現在も芝居を続けている谷さんに脚本や演出をお願いしました。こうしてできたのが、第1回にあたる『ヒヤリ・ハット劇場』です。
- 谷
-
といっても、第1回目は5分足らずの寸劇で、出演者もまだ3人だけでした。ちなみに、寺口さんの役はピカチュウ。患者さんが、インスリンの「皮下注」を「ピカチュウ」と聞き間違えたという設定で、「ピカチュウ?」しか言わない役です。これがウケたんですよ(笑)。それ以降は、『接遇劇場』『守秘義務劇場』『接遇最前線』と毎年上演し、2005年の『エンゼルメイク劇場 ほほえみの結晶』は3年連続で再演しました。

回を重ねるごとにどんどん規模が大きくなっていったようですね。演者さんとなる職員のみなさんは積極的に参加してくださいましたか?
- 谷
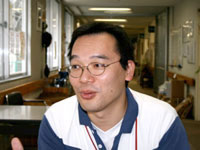
ナース・谷進一さん(ぬくもりの里勤務)。
脚本・演出・音効などすべてを担当している
第2回、3回と劇の内容が膨らんでいったのは、伝えたいことをより多く盛り込んだからです。またセリフにもこだわり、たとえば『接遇最前線』では、「ポータブルトイレの便は臭いから早く捨てて!」など、実際に患者さんからお叱りをうけた言葉をそのまま使うなどしてリアルな雰囲気を演出しました。あくまでも研修の一環ですからね。現場における課題を実感してもらわないと。
- 寺口
-
そうですね。そんなクオリティへのこだわりが、人気につながったのだと思います。私も毎回、楽しく出演させてもらっていますし(笑)。
- 谷
-
寺口さんを筆頭に(笑)、職員のみなさんは思った以上にノリノリで演じてくれますね。基本的には初心者ばかりなので恥じらいもありますが、慣れていくうちにどんどん“隠れた自分”を出してくれます。みなさん、芸達者ですよ。演出側としては面白い“発見”です。予想以上に上手くなったので、第4回の『接遇最前線』からは職員以外の方にも見ていただき、第5回の『エンゼルメイク劇場 ほほえみの結晶』では大阪のシアトリカル應典院など、院外の施設でも上演することができました。

大人気により再演につぐ再演となった『エンゼルメイク劇場 ほほえみの結晶』ですが、このテーマを取り上げようと思ったのはどうしてですか?
- 寺口

『ほほえみの結晶』のチラシ。イラストは
なんと寺口看護部長の手書き!
当院では以前より、感染管理委員会やインシデント委員会などで学習会を盛んに行ってきました。あるとき、ターミナル緩和ケア委員会のメンバーから、亡くなった患者さんに生前の面影を取り戻す『エンゼルメイク』について勉強したいという声が上がったんです。当院ではそれまで、死後処置については多くの疑問点を感じながらも、残念ながら目立った改善は行われてきませんでした。これではいけないと、2004年12月に小林光恵先生(作家・エンゼルメイク研究会代表)をお招きし、エンゼルメイクの必要性から手順の見直し、エンゼルセットの検討までをご教授いただいたんです。この講演をきっかけに、2005年2月に『エンゼルケア委員会』が発足。感銘を受けた私たちは、この看護をもっとたくさんの人に知ってもらいたいと、院内劇場のテーマに採用したという流れです。

奥田さんは『エンゼルケア委員会』に所属し、さらに『エンゼルメイク劇場 ほほえみの結晶』にも出演されたそうですが、どんな感想を持たれましたか?
- 奥田

明るい笑顔が印象的なナース・
奥田真弓さん。患者さんの人気者
出演したといっても、私は亡くなった患者さん役だからセリフは無し(笑)。でもそれで良かったんですよ。おかげであまり緊張せず、他の演者さんの演技をじっくり観察することができました。そうして気づいたのが、ナースによる声かけの大切さ。「そういう役だから」と言ってしまえばそれまでなんですが、みなさん本当に優しく声かけしてくれるんですよ。思わず、自分の日々の声かけを反省してしまいました。言葉ひとつでこんなにも癒されるんだなって。
それに、この劇がきっかけで、エンゼルケアが大好きになったんです。エンゼルケア委員会に入ったのもそれからです。以後、患者さんができるだけ生前に近いお姿に近づけるよう、マッサージの方法やメイクアップの技術などを研究したり、新入職者や復職者向けのエンゼルケア学習会を実施したりと、私たちだけでなく病院全体で知識を共有できることをめざしています。
エンゼルケアは、私たちにとって最後にできる大切な看護です。ご家族の方のグリーフケアにもつながるので、もっと多くの人に伝えたいですね。

『院内劇場』を通して得た成果や課題、また今後の目標などを教えてください。
- 奥田

劇中の寺口看護部長。奥田さんはベッドで
眠りながら一人ひとりの演技に感動中
一般のお客さんを含め、多くの人がエンゼルケアに興味を持ってくれたことが良かったですね。他病院で働く友人に公演のDVDを見せると、それがきっかけでその病院でエンゼルケアの院内学習が行われたなんて例もあるんですよ。
- 谷
-
僕は正直、初めは自分の経験を活かした表現活動の一環としか考えていませんでしたが、職員同士の交流、医療情報の交換など、予想以上のメリットがたくさんありました。特に『エンゼルメイク劇場 ほほえみの結晶』では、他病院から参加してくれたキャストもいましたからね。今後は、演劇だけではなく映像版にチャレンジしたいという声も上がっています。
- 寺口
-
研修時には過去の公演のDVDを鑑賞することがあるのですが、みんな楽しんで学んでくれているようです。ときには新人ナースよりも、中堅以上のナースが、「こんなことって今でもあるよね」「気をつけなきゃね」なんて言いながら楽しんでいる風景も見かけます。もう数年前の劇ですが、看護をしていくうえで切っても切り離せない課題を取り上げているせいでしょうね。初心に帰るための良い題材にもなっていると思います。

最後に、看護学生に向けて何かメッセージをお願いします。
- 奥田
- 自由な風土のなかでのユニークかつ真剣な取り組みが、当院の特徴の一つです。私がこんなにエンゼルケアを考えるようになったのも、院内劇場のおかげですから。当院で働く方には是非どちらも体験してほしいです。
- 谷
-
そうですね。当院には、その人の能力が予想外のカタチで活かせるような雰囲気があると思います。教育・研修の一環として広がった院内劇場が、地域の方々や看護学生のみなさんとの交流に役立てば幸いです。
- 寺口
-
院内劇場で一人ひとりのキャラクターを“発見”したように、当院では一人ひとりの個性を伸ばす教育・研修を心がけています。より良い看護体制を基盤に、『看護で選ばれる病院』をめざしています。みなさんが新しい仲間として加わってくださる日を楽しみにしています。

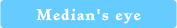
同院看護部では、ナース一人ひとりが“点”ではなく“線”として機能し、患者さんと関わることをめざしている。その意味で、院内劇場はまさに“線”の取り組み。職歴も年齢も部署も異なる職員同士が手を取り合い、病院として果たすべき課題を考察、医療の質向上につなげている。また、この個性的な取り組みが実現したのは、役者経験を持つ谷さんの活躍が大きいが、そんな持ち味も寺口看護部長の“理解ある遊び心”の上でこそ活かすことができたと言える。誰よりもナース一人ひとりの個性を発見したいと望む、寺口看護部長らしい教育風土だと感じた。











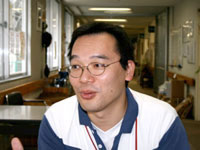



![]()