Pick Up Hospital

NST・緩和ケアチーム・褥瘡委員会・訪問看護etc…さまざまなナースによるさまざまな看護のカタチを徹底レポート!
※掲載されているデータは取材当時のものです
Pick Up Hospital 5 [ 2009.10 ]
競技もコスプレも真剣勝負!
予期せぬ急変に強くなる個性豊かな教育・研修。
ある患者さんが食事中に突然苦しみ出しました!予想外の緊急事態に看護助手が慌ててナースを呼びに行きます。そこに駆けつけたのは、セーラー服を身にまとった男性ナース。……これは一体!?
これは大阪府済生会千里病院が、ナースのスキルアップのために行っている『院内メディカルラリー』のワンシーン。ナース数名でチームを組み、与えられた想定場面に対していかに適切にケアできるかを競うものです。“コスプレOK”という遊び心満点のイベントですが、内容は打って変わって真剣そのもの。救命センターを併設する同院ならではのイベントを取材してきました。
社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会千里病院
〒565-0862 大阪府吹田市津雲台1-1-6
TEL:0120-73-1504(担当/看護部長室)
E-mail:
jinji234@crest.ocn.ne.jp
■開 設 年/平成15年
■病院長/林 亨
■看護部長/石井美津子
■病 床 数/343床(一般300床、救急病棟31床、ICU12床)
■職 員 数/約760名
■内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、産科、婦人科、泌尿器科、小児科、歯科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、心療内科、精神科、神経内科、放射線科、麻酔科、救急科、病理診断科
■看護配置/実質配置 7 : 1
■外来患者/534名(1日平均)
■入院患者/320名(1日平均)
■交通案内/阪急千里線「南千里」駅下車すぐ
■その他/看護大学・看護学校(全日制3年課程)や認定看護師の実習指定病院(救急看護、皮膚・排泄ケア)、日本医療機能評価機構Ver.5.0認定病院
院内メディカルラリーの効果とは?

- 看護部長
石井美津子さん

院内メディカルラリーは今回で第3回目となるそうですね。どうして院内で行うようになったのでしょうか?(Median編集部)
- 石井

石井美津子 看護部長。今回も迫真の
演技で患者さん役を務めた
プレホスピタルの症例を対象としたメディカルラリーは、2001年に千里メディカルラリーを開催して以降、全国各地で開催されるようになりました。当院でインホスピタル(院内)におけるメディカルラリーを行うようになったのは、2006年秋にスタッフナースが看護部長室に持ち込んだ企画書が発端です。当院で看護に従事するすべての看護職の知識・技術の向上を図ることを期待して作成された企画書で、急変時対応力、TPOを考慮したチーム医療としての判断力、必要最低限のスキルの習得・実践および指導力を身につけることをめざした内容でした。
競技者たちのメリットとして、現時点での自らの知識・スキル・判断の客観的評価を受けて今後の課題を理解し、不足している知識と技術への自発的な向上が望めます。とても面白い企画でしたので、表に出るのはスタッフナースたちとし、管理職は裏方に回りサポートに徹して実現させようと考えました。一部のやりたい者だけで開催するイベントという印象を与えないよう、ネーミングは看護部主催とし、病院施設の使用など予算面も考慮して、院長決裁を仰ぎました。林亨院長はじめ、他部署・他職種の温かな協力を得ることもできました。

院内メディカルラリーの具体的なプログラムを教えてください。
- 石井

オリエンテーションを聞く競技者たち。
コスプレも気合い十分!
具体的なプログラムもすべてコアスタッフが作成しました。外来、病棟、その他で起こり得る場面を想定した3ステージと、筆記問題や他者への指導力を問う2 つのスペシャルステージを用意しています。それをナース3名で構成された複数のチームが指導係の指示通りに回り、1ステージ10?15分くらいでチャレンジします。
競技中は、何をするのか、何を見ているのか、すべて声に出してアピールしてもらいます。でないと、競技者が何を考えてその行動を取ったのかが評価者に伝わりにくく、評価しづらいので。

ステージ1の『低血糖症例』では、特にどの点を評価のポイントに置かれたのでしょうか?
- 石井

優しく話しかけながら患者さんの
状態を確認する競技者たち
ここでは、『バックグラウンドを知らない患者さんの急変対応』がテーマなので、情報収集の大切さがポイントでした。私が演じた定期採血のため来院した糖尿病の患者さんは、採血後低血糖による気分不良が出現したという設定です。「今日の看護師さんは失敗ばっかり!3回も刺されたの!」と、採血の失敗で気分が悪くなったのかなと思わせる役どころでした。
競技者が『来院の理由』『患者さんの既往歴』『主治医の名前』など必要不可欠な情報の収集ができれば、そこから『主治医への連絡』『気分不良への原因対応』『薬剤使用時のダブルチェック』など、ストーリーとチェック項目が展開していきます。

ステージ2の『吐血症例』では、チームによってさまざまなケアの過程があったのが印象的でした。
- 石井

シナリオは最後まで進まなくても、
時間がくれば競技終了となる
ステージ2は、『急変患者のショック症状を観察し、ショックの進行を防ぐ』がテーマでした。既往歴に脳梗塞と心筋梗塞を持つ患者さんがトイレで吐血し、ナースが急いで駆け寄るのだけれど、患者さんは「大丈夫」と言い張る……というシナリオです。患者さんの安全を確保し、ドクターハリー(院内の緊急時召集システム)を正しく使えるか、また速やかな挿管準備と適切な介助技術ができるか、加えて、リーダー役のナースはしっかりとしたリーダーシップを発揮できるかなどをチェックします。ときには駆けつけたドクターが、競技者に次々と質問を投げかけてワザと戸惑わせたりすることも。さまざまなケアの過程が生まれたのはそのせいかもしれませんね。ナースたちは悩みますが、チームでしっかりと考え確認しながら答えを出すようになります。

ステージ3の『窒息CPA症例』は、認知症と食事がテーマでしたね。
- 石井

格好とは裏腹に真剣そのもの!
そうですね。ここでは認知症があり、脳梗塞で右半身が麻痺状態の患者さんが食事中に突然苦しみ出すというシナリオです。ひきつけを起こしている患者さんに対し、いかに迅速に必要な人員や物品を集めることができるかが重要でした。
患者さんはその後、CPA(心肺機能停止状態)になってしまう設定なので、気道確保や呼吸・循環の確認などは正確でなければなりません。「呼吸なし」「循環のサインなし」の判断の後は、CPAに対するケアの審査に切り替え、絶え間ない胸骨圧迫ができるかをチェックしました。

シナリオはすべて貴院の実状を反映して企画されているとか。企画者となるコアスタッフの方々は大変だと思うのですが・・・。
- 石井

コアスタッフの田中美保さん(左)、
藤巻ゆかりさん(中央)、
荒瀬典子さん(右)
企画から運営まで、コアスタッフのメンバーは本当によくやってくれましたし、運営スタッフなど参加者全員のチームワークがあってこそのラリーでした。
この競技の醍醐味は、座学では学べない急変時の臨場感とチームワークの重要性を体験できるところです。多くの事例を体験することで急変を予測でき、治療参画がスムーズに行えるようになればと想定して企画する訳ですから、準備には相当なエネルギーを費やしています。その分、楽しみながら学んでいく競技者の姿を見て、大きなやりがいを感じたと思います。

コスプレもあるせいか、皆さん楽しそうでしたね。閉会式後の懇親会では、『コスプレ賞』も発表されますし(笑)。
- 石井

見事、林院長のハートを射止めたのは
『チームアラサー』の皆さん!
林院長のご理解もあって、遊び心を大切にしているんです。おかげで、いろんな個性がぶつかりあっているでしょう?(笑)それに、イベントの当日は朝8時半に集合して、振り返りを含めると18時前まで延々と続くので、結構ハードです。だから表彰式と懇親会では大いに楽しんでもらいます。コスプレ賞もその一環です。
懇親会では、カメラ係が撮影した静止画・動画をスクリーンに映して、全体の様子をじっくり見直して大いに盛り上がります。優勝カップの授与のほか、上位3チームとコスプレ賞チームには、チームの写真入り賞状を渡しています。

最後に、今回の院内メディカルラリーを終えてのご感想をお願いします。
- 石井

第3回のチャンピオンは『モォモォ』
に決定!
私は今回を含む過去3回のラリーでも患者さん役を担当しました。患者さんになりきって演じていると、医療従事者の視点では気づきにくいことをたくさん実感できます。「石井さんですね、私は○○と申します。今から?を行いますね」と笑顔で説明してもらうとホッとし、素早くてきぱきと応援を要請している姿は頼もしく見え、「大丈夫ですからね」と耳元で状況を伝えてくれる声に励まされ、薄れゆく意識の中でもう少しこうしてくれればと思うこともあり……。今後、強化していかなければならない課題も含め、このラリーを通して『予期せぬ急変への適切な対応力』とはどういうものかを改めて考えるようになりました。企画者と参加者の『能力』『やる気』『思い』が合わさり、予想以上に有益な教育・研修の場になっています。
第4回目となる2009年度からは実行委員会形式にし、企画・運営スタッフの育成を繋いでいきます。準備段階を含め、各役割を担うスタッフたちが成長していく姿を見ることができ、とても幸せです。

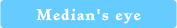
院内メディカルラリーから数日後、石井看護部長のもとに競技に参加したナースたちからメールが届いたそうだ。内容は、「とても勉強になりました」や「普段から急変対応について意識するようになりました」「通勤コースのAED配置などを確認するようになりました」といった前向きなものばかり。研修というと、ときに“やらされている感”も芽生えるものだが、同院の場合はまったく違う。職員が自主的に参加し、楽しみ、そして真剣に学んでいる。競技者を飽きさせない魅力的なアイデアと、遊び心満点のアットホームな雰囲気が上手く機能している証拠だろう。












![]()