Pick Up Hospital

NST・緩和ケアチーム・褥瘡委員会・訪問看護etc…さまざまなナースによるさまざまな看護のカタチを徹底レポート!
※掲載されているデータは取材当時のものです
Pick Up Hospital 12 [ 2011.7 ]
増え続ける透析患者さんの命を預かる腎臓病センター。
ワンフロア105床の施設で、患者さんを見守る看護師たち。
国内で慢性透析療法を受けている患者数は、2009年12月時点で290,675人であり、これは前年度より8,053人増加している(日本透析医学会調べ)。それよりさらに遡ると増加数は、2008年末で7,503人、2007年末で10,646人、2006年末で6,708人、2005年末で9,599人であった。増え続ける患者数の背景には、生活習慣病などの合併症により腎機能が低下し、透析を受けるケースが少なくない。透析は一度受けるとその後継続して受け続ける必要がある。一生のおつきあいとなるわけだ。そんな身体的にも精神的にも制約のある透析患者さんを支えるのは、医師はもちろんのこと、看護師、臨床工学技士、栄養士、薬剤師たちである。
今回は、大阪市内でもトップクラスの施設を持つ大野記念病院腎臓病センター師長代理の川上百合子さんと看護師の川端亜紀さんに、病棟とは違った特殊性のある透析看護の仕事内容ややりがいについて伺った。
医療法人寿楽会 大野記念病院

▲大野記念病院 外観写真
〒550-0015 大阪市西区南堀江1-26-10
TEL:06-6531-1815(代)
URL:
http://www.ohno-kango.com/
■開 設 年/大正13年1月1日
■開 設 者/医療法人寿楽会
■理 事 長/大野 良興
■院 長/岡村 幹夫
■看護部長/西村 加代子
■病 床 数/250床(一般)、105床(透析)
■職 員 数/390名
■特殊機能/救急指定、労災指定
■外来患者/500名(1日平均)
■看護配置/実質配置10 : 1
■敷地面積/2,260.4㎡
■建築規模/鉄筋コンクリート造り、地上11階、地下2階
■認 定/(財)日本医療機能評価機構認定病院、開放型病院、臨床研修指定
■寿楽会グループ/
・大野クリニック(人間ドック)
大阪市中央区難波2-2-3 / TEL(06)6213-7230
・m・oクリニック(集団健診)
大阪市西区南堀江1-18-21 / TEL(06)6533-6760
・寿楽会クリニック(人工透析)
大阪市天王寺区大道4-1-11 / TEL(06)6779-1226
・介護老人保健施設『箕面グリーンビィラ』
箕面市粟生間谷東1-33-25 / TEL(072)727-3475
■交通案内/地下鉄、近鉄ナンバ駅、JRナンバ駅より西へ7分、
南海ナンバ駅より北西へ10分、地下鉄桜川駅5番出口より北東へ5分

▲大野クリニック(人間ドック)
▲m・oクリニック(集団検診)
▲寿楽会クリニック(人工透析)
▲介護老人保健施設
『箕面グリーンビィラ』
多くの血液透析患者さんを受け入れるために、活躍する看護師たち。

- 腎臓病センター師長代理
川上百合子さん

- 看護師 川端亜紀さん

最近の透析を受ける患者さんの傾向について、お聞かせください。
(Median編集部)
- 川上
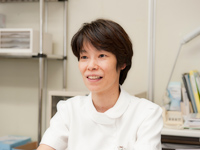
腎臓病センター 師長代理 川上百合子
そうですね、私が初めて透析看護に携わった頃と比べると、今は慢性的に腎臓だけの機能が低下するというより、生活習慣病、例えば糖尿病や高血圧の長期罹患により腎臓の機能が低下して透析が必要になるケースや、高齢化により60歳以上の方が発症し来院されることが増えています。また、検査入院や教育入院で、将来透析に至らないように予防策をとるようにもなっています。
最近では、腹膜透析(CAPD)や腎移植に移行される方も徐々に、増えてきました。どの治療方法を選ぶかは、メリット・デメリットを医師が説明し、その中から患者さんに選択していただいています。

それぞれの特徴を教えてください。
- 川上

簡単にご説明しますと、血液透析は、拘束される時間が一番長く、平均して週2?3回、1回につき4?5時間かかります。針を刺す痛み、水分・食事制限がありますね。最近では夜間透析のできる施設も増え、働きながら透析を続けている方も増えたのではないでしょうか。腹膜透析は、腹膜の中に2リットル近くの液を貯蔵し、68時間貯めておく必要があり、その後廃液して毒素を体外に出していくわけですが、通院は少ないけれど自己管理する負担があります。事前に教育指導を受け、専用の部屋を用意することも必要になります。腹膜炎や出口部感染を起こすリスクはありますが、旅行にも行けますし、水分・食事制限は血液透析より軽くなります。腎移植は、ヒト白血球型抗原(HLA)型が適合するドナーを待つことになります。腎臓は左右一対あり、正常な腎機能であれば片方でも機能しますから親子・兄弟・夫婦からの提供も可能です。しかし、両者共に手術という負担はあります。最近では臓器提供意思表示カード(ドナーカード)を持つ人も増えており、移植の可能性は広がっていると思います。当センターでも1年以内の間に2人、移植に移行された方がいらっしゃいました。

こちらでの血液透析の現状を教えてください。
- 川上

当センターは、血液透析をワンフロアで行っており、105床のベッドを持っています。現在400名近い患者さんが通院されています。これだけ大きな施設は大阪市内でもトップクラスです。ワンフロアなので、スタッフの動線の短さや急変時への対応が取りやすいメリットがあります。受け入れ時間は朝8:00?夜22:00まで、夜間緊急対応もしています。受け入れスタッフ(先生以外)は、看護師31名、臨床工学技士20名が勤務しています。場合によっては栄養士や薬剤師なども加わり、チーム医療体制で患者さんを支援しています。ベッド稼働率は、午前中ほぼ満床で、午後はもう少し減りますが、16:00から夜間透析を20?25名受け入れているので、フル回転です。

中でも特徴的な取り組みなどはありますか?
- 川上

去年の12月から病棟でも血液透析を開始しました。今までは入院している方がどんな状態でも、こちらのセンターまで車椅子やエレベーターで移動してもらっていました。手術後の方、呼吸器を着けている方、血圧低下する恐れのある方などすべてです。これらの患者さんの負担を軽減するために、病棟での透析を開始しました。病棟透析導入にあたっては、設備を導入することはもちろんですが、その環境を維持するために臨床工学技士が大きくかかわっています。さらには病棟看護師にも透析の知識が必要になるということで、こちらで透析患者さんの身体状態の理解や透析のやり方、備品の取り扱いなどを研修しました。

今回の東日本大震災では、被災地で透析患者さんの受け入れできる病院の情報がTVやインターネットで流れました。透析は命にかかわる大切な治療なのですね。
- 川上

透析には水と電気が必要ですから、災害等でライフラインが止まると実施したくてもできなくなります。そんな場合は、自家発電などによって稼働している施設に行っていただくしかありません。今回の震災後、栄養士が中心となって患者さんへの勉強会を開きましたら、たくさんの参加があったと聞いています。内容は、もし透析が受けられなくなった時に自分はどれくらいもつのか、日頃からどのような自己管理をしておけばよいのかなどをご説明しました。終了後には参加した方から、「とても参考になった」「これからは日頃の生活を改めようと思った」等の声が聞かれ、大変好評だったようです。

透析看護の特徴ややりがいは、どのような点でしょうか?
- 川上

透析看護の仕事は、朝、透析機械に必要な血液回路の確認、薬剤の準備等から始まります。それを臨床工学技士と組んで行い、受付時間になったら、朝一番の患者さんを10名ほどお迎えします。透析は一度導入すると長いですから、患者さんとの関わりも長期に及びます。患者さんとコミュニケーションがうまくとれて、信頼が得られた時に、悩みを相談されたり、透析治療がうまくできている姿を見ていられることがやりがいだと思います。長い患者さんですと30年近くつきあっています。長ければそれだけ患者さんの方が透析についてはベテランです。新人看護師より知識がありますから、新人看護師ははじめ少し大変かも知れません。でも焦らないで、日々の経験を積みながら成長していくことだと思います。また、当センターにはスタッフがたくさんいますから、カンファレンスなどを開いて頻繁に情報共有もしています。みんなの力でたくさんの患者さんを支えているという実感は得られると思います。

逆に苦労する点や難しい点は?
- 川上

透析は長い時間同じ姿勢を保持したり、定期的に通い続けたりすることが必要ですので、時には「あ?しんどい」「早く死にたいな?」などとネガティブになられることもあります。そんな時、看護師に必要なことは、落ち込んでいる患者さんに、明るい笑顔で話しかけられること。笑顔が素敵で、思いやりと厳しさを兼ね備えていることが求められると思います。制限のある中で、いかにその人に合った接し方や話し方ができるかが難しい点です。また、スタッフによく言うのは、「私たちは命を預かっているのですから、淡々とやってはいけない」ということです。そうならないために、患者さんの変化に気づくことや患者さんが気兼ねせずに過ごしてもらえるような配慮ができるように心掛けて欲しいですね。

教育面ではどのようなことをされているのでしょうか?
- 川上
-
当センターは、平均年齢も若く、活気のある職場だと思います。第一段階の目標は、入職後1年後にはリーダー業務ができるようになることです。でも個人差はありますから、一律にはしていません。先輩達が、新人の個性を大切にしながらその人に合った指導をしていきます。共通して言えることは、仕事を覚えることに積極的で自分で調べたり聞いたりできる人は、成長が早いということです。
新人看護師は入職後すぐに他科の人たちと一緒に集合研修を行い、その後配属が決まります。さらに去年から導入しているローテーション研修によって、各科を1ヵ月位経験することができます。その後配属換えもできますから、ゆっくりと自分の適性を見て選ぶことができるようになっています。

最後に川上さんが、透析看護で大切にしていることは?
- 川上

患者さんが分かりやすい説明を心掛け、納得してもらえるように話すこと、それに患者さんが気兼ねしないで機嫌良く過ごしてもらえること。そのために声をかけやすい、聞きやすい雰囲気作りを大切にしています。同じ時間を過ごすならいい雰囲気の中で気持ちよく過ごしてもらいたいですし、その方が看護する私たちも嬉しくなりますからね。
あと、透析のない日の自宅での生活をお聞きして不安はないかをフォローすることもあります。患者さんから「昨日は家でこうやったんよ」と話してもらえるような関係作りができたら、一人前ですね。マニュアル通りにはいかない看護ですが、工夫次第で結果は伴ってくるので、それがまたやりがいにもつながっていくのではないでしょうか? 一人でも多くの方に透析看護の魅力を知っていただきたいと思っています。


| 透析看護に携わって2年目になります。それ以前に病棟看護の経験はあったので、視野を広げるために腎臓病センターを希望しました。学生の時に実習で透析看護は見たことがあり、興味をもっていました。でも慣れるまでは、備品の扱い方や機械の見方など覚えることもたくさんあって大変でした。最近、やっと少し見えてきたかなといった状態です。実際に担当してみると、患者さんは4?5時間、制約されるわけで、看護師としてどのように関わったらよいのかは、迷いました。でも患者さんのデータが良くなって改善の兆しが見えた時にはそのことをお話して、一緒に前に進んでいけるので、その点にやりがいを感じます。つい最近、看護研究を院外で発表してきました。院外の状況を知ることは勉強になりましたし、また頑張ろうという意欲がわいてきました。当面の目標は、もっと透析看護の知識を増やし、極めていって、患者さんに適切なアドバイスができるようになることです。
|

腎臓病センター看護師 川端亜紀さん |
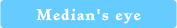
今回訪問した大野記念病院腎臓病センターは、ワンフロアに105床を有する大きな施設だった。ここに400名もの透析患者さんが定期的に通い続けている。今年3月の東日本大震災発生直後に、被災地の透析患者さんを受け入れ可能な施設がTVのテロップで流れていた。透析施設は透析患者さんにとって命綱なのである。多くの患者さんの生命をつないでいる透析看護のスタッフ達。病棟での看護とはまた違った責任と手応えを感じた。









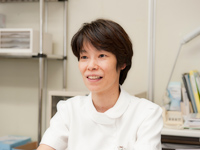












![]()