Pick Up Hospital

NST・緩和ケアチーム・褥瘡委員会・訪問看護etc…さまざまなナースによるさまざまな看護のカタチを徹底レポート!
※掲載されているデータは取材当時のものです
Pick Up Hospital 4 [ 2009.8 ]
退院後の快適な生活を支援するエキスパートナース。
受け持ちナースによる“入院から退院まで”というフレーズはよく耳にしますが、では、“退院後の支援”も必要とする患者さんにはどのようなサポートが必要なのでしょうか。今回は、早期から退院支援活動の重要性に目を向け、患者さんにとって最適な在宅・療養生活の実現に取り組んできた岐阜県総合医療センターの『退院調整室』の取り組みを紹介します。
岐阜県総合医療センター
〒500-8717 岐阜市野一色4-6-1
TEL:058-246-1111(代) 担当/看護部
E-mail:
c22601@pref.gifu.lg.jp
■開 設 年/昭和28年
■病 院 長/渡辺 佐知郎
■看護部長/高木 久美子
■病 床 数/590床
■職 員 数/800名
■診療科目/総合内科、糖尿病・内分泌内科、精神科、循環器内科、腎臓内科・透析部、消化器内科、肝臓内科、血液内科、神経内科、呼吸器内科、小児科、小児循環器内科、新生児内科、外科・消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児心臓外科、小児外科、小児脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産科・婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、放射線診断科、歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科
■看護配置/実質配置 7 : 1
■重点医療・機能/救命救急センター(救命救急医療)、心臓血管センター(心臓血管疾患医療)、母とこども医療センター(周産期医療)、がん医療センター(がん医療)、女性医療センター(女性医療)、基幹災害医療センター(災害医療)
■各種認定・指定/
〈研究施設認定〉臨床研修指定病院(医科)、臨床研修指定病院(歯科)、外国医師臨錬指定病院、日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設、日本循環器学会専門医研修施設等
〈機関指定〉保険医療機関、国民健康保険指定病院、労災保険指定病院、救急告示病院、基幹災害医療センター、地域がん診療拠点病院、特定疾患治療研究受託病院等
〈公費負担医療制度指定〉労働災害、救急指定、特定疾患、戦傷病者、原爆医療、養育医療、精神保健、麻薬取締、結核予防、生活保護
■交通案内/岐阜バス(JR岐阜バス、名鉄岐阜バス)・岐阜県総合医療センター下車すぐ
退院調整看護師に聞く!

- 吾郷(あごう)佐代子さん

- 増井法子さん

- 丹羽好子さん

- 宮木久美さん

- 武山博子さん

まずは『退院調整室』設置の経緯について教えてください。(Median編集部)
- 吾郷

病院連携部をまとめる吾郷 看護師長
医療制度の特性を活かした機能分化が進むなか、在院日数の短縮化とともに、“急性期病院から地域・在宅へ”という医療連携が求められるようになりました。当院看護部でもそのような意識が高まり、退院後の生活をサポートする専門の部署・ナースが必要だということで、2001年に退院調整看護師を1名配置したんです。当初はまだ試行という形で、専任ではなく外来看護との兼任で行っていました。
- 増井
- 2002年からは私も加わり2名となるのですが、依頼件数が増えるにつれパンク状態に……。私たちの活動内容が認知されるにつれ、「こんなことまでやってくれるんだ!」と、病棟ナースの人気者になったようです(笑)。そうした経緯から2005年からは専任業務に発展し、同時に『病診連携部』が誕生。地域の診療所や介護サービス機関との連携をはかる『地域医療連携センター部・病診連携部』所属の『退院調整室』として、現在は退院調整看護師4名、ケースワーカー1名で活動しています。

依頼から実施まで、具体的な退院支援活動の流れを教えてください。
- 丹羽

増井さん(左)と丹羽さん(右)
増井さんはリーダー的存在として活躍
まず、脳血管疾患やがん緩和ケアなど、退院調整の必要がありそうな患者さんをスクリーニングにかけ(入院から48時間以内)、該当項目にあてはまれば主治医や受け持ちナースから依頼がきます。依頼を受ければ退院調整室で介入の必要性などを検討し、患者さんやご家族と面談を行います。その後はご希望に応じて地域の医療機関と連携し、関係者全体でのカンファレンスを繰り返しながら、細かな調整を行っていきます。退院前には『退院前カンファレンス』、自宅療養を希望される方には、病棟ナースとともに患者さんの自宅を訪れる『退院前訪問』などを実施し、訪問看護師や理学療法士と情報交換して退院後の生活について考えます。すべてを取りまとめるコーディネーターとして、いつも院内外を駆け回っていますね(笑)。
- 増井
-
ちなみにスクリーニングシートについでですが、これは2004年?2006年に岐阜県が保健事業の一環として行った『地域連携と退院調整推進事業』に検討委員として参加し、県内のスクリーニングシートすべてを調査したうえで、当院に最も適している項目や書式を作成しました。まだまだ多くの改善点を残していますが、「誰が見ても分かりやすい」と一定の評価を得ています。

長期入院の患者さんに対してはどのような対策を取られているのでしょうか?
- 宮木

宮木さん(左)、武山さん(右)
活動が本格化した2005年より、毎月初めに1ヵ月以上の入院患者さんを全病棟からリストアップし、退院調整看護師が各病棟をラウンドします。ラウンドには地域医療連携センター部の責任者である小林成禎医師も同席し、長期入院に至った理由や現在の治療法、今後の見通しなどをヒアリング。後日、主治医からの回答を院長自らもチェックし、退院調整室の介入が必要なら即座に対応するようにしています。
- 武山
- この“医師と連携して行う”ことに意味があるんです。患者さんも医師から説明される方が安心されるし、納得もされます。私たちとしても非常に動きやすいですね。病院全体が同じベクトルに向かって取り組めているおかげで、長期入院患者さんの割合は明らかに減少しています。ちなみに、2005年の平均在院日数 15.7日から、2008年は13日まで短縮することができました。

主治医はもちろん、病棟ナースとの連携も重要になりますよね。退院支援活動への理解を深める教育プログラムなどがあるのでしょうか。
- 増井

退院支援カンファレンスを行う
丹羽さん。病棟ナースの意識改革
のため週1回実施
『継続看護推進委員会』のなかで、具体的な援助技術、事例検討、介護保険に関する知識など、退院支援を推進するための教育プログラムを設けています。地域のケアマネジャーや訪問看護師、場合によっては開業医の方を外部講師として招聘することもあり、在宅医療についての実践的な知識が身につくと思います。
これは以前、自主的なクラブ活動として行っていたのですが、ナース個人の学びではなく、病棟・部署にも浸透させる必要性が増してきたことから、2008年より組織的な取り組みに発展を遂げたものです。
- 吾郷
- 退院調整に関するスタッフ教育は2005年から行っていますが、多くのナースが、“入院から退院後の生活まで”をしっかり考えてくれるようになったと思います。退院調整看護師に頼るのではなく、自分たちで工夫し、患者さんに適した退院・療養指導をしようと頑張ってくれています。この調子で、退院支援を取りまとめるリーダーを一人でも多く育てたいですね。

患者さんやご家族の反応はいかがでしょうか?
- 武山

長期入院する患者さんの状態を
チェック。中央が責任者の小林医師
基本的にはご理解いただいていますが、「どうして追い出すんだ!」とお怒りになる方もいらっしゃいますし、反対に「自宅で看てあげたいので退院させてください」と言ってくださるケースもあります。いろいろですね。がん患者さんの場合だと、「まだ動けるうちに帰りたい」とおっしゃるケースも少なくないのですが、じゃあご家族に自宅療養を受け入れる体制が整っているかというと、必ずしもそうではありません。私たちが間に立ち、柔軟な解決策をもって接することが求められます。
- 宮木
- 自宅療養の場合、それはご家族の生活に直結しますからね。退院調整看護の難しい部分だと思います。私が最も印象に残っているのは、「大切な家族が退院を望むなら、できることは何でもしてあげたい」というご家族からのお言葉。これは本当に感動しました。まだ退院は難しい状態だったのですが、「この人たちのために頑張ろう!」と力が湧いてきましたね。

特殊性のあるお仕事ですよね。しかしその分、やりがいも多いと思うのですが。
- 丹羽

ご家族も含めた合同カンファレンス。
それぞれの立場から最適な案を模索する
すべてをやり遂げたときの達成感は大きいですね。ただ最も大切なのは、いい意味で八方美人になることかもしれません。ご希望のすべてにマッチングできるとは限らないので、何らかの妥協点を探し出すことも必要になってきます。もちろん、患者さん、ご家族との信頼関係があってこそ可能になる作業です。
- 増井
- 患者さんの退院後の暮らしと健康のあり方について考え、その具体策を支援することって、単純にスゴイ仕事だと思うんです。言い換えれば、患者さんの今後の人生を左右するかもしれない局面に立ち会っているのですから。転院一つをとっても、患者さんの病状、経済状況、転院先の医療充実度、アクセスなど、あらゆる点を考慮して一緒に答えを導き出していきます。
また丹羽の言うように、すべての患者さんがベストな状態で退院できる訳ではありません。しかしそれも、患者さんやご家族の“人としての成長を支援する”ことで取り返すことができるんです。小児科を例に挙げるなら、人工呼吸器をつけたお子さんの自宅療養に対し、最初は不安しか口にしなかったお母さんが、私たちの指導で日に日にたくましくなっていかれる……。そんなステキな時間を共有できるから、この仕事はやめれないんです。
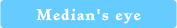
平均在院日数12?13日という急性期病院のなかで、入院時から退院後の生活にまで視野を広げて看護するのは簡単なことではない。しかし病気や障害を抱えた患者さんやその家族にとって、退院後の生活は入院生活以上に不安な要素でもある。だからこそ、地域の関係機関との中心窓口として機能し、組織的な退院支援教育に取り組む同院の信頼は厚いのだろう。このペースでいけば、病棟ナースによる独立した退院支援活動が盛んになる日も近いのではないだろうか。














![]()