Pick Up Hospital

NST・緩和ケアチーム・褥瘡委員会・訪問看護etc…さまざまなナースによるさまざまな看護のカタチを徹底レポート!
※掲載されているデータは取材当時のものです
Pick Up Hospital 9 [ 2010.6 ]
真のチーム医療を提供するために、
看護の専門性を活かして、積極的に活動する認定看護師。
今、多くの病院で看護のスペシャリストが活躍しています。全国で認定看護師5,762名、専門看護師451名(平成22年6月現在)という数字からもわかるように、その数はますます増え続けています。
資格は取ることが目的ではなく、その後いかに臨床現場で反映させていくかが大きな鍵となります。
今回は、長野県松本市の相澤病院に勤務するある認定看護師の活動を追ってみました。
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院

▲地域医療支援病院として松本市
および周辺住民の健康を支える

▲24時間、救急医療現場は眠らない
〒390-8510 長野県松本市本庄2-5-1
TEL:0263-33-8600(代) 担当/人事部
E-mail:
jinjipr@ai-hosp.or.jp
■開 設 年/1952年1月26日
■病 院 長/相澤 孝夫
■看護部長/武井 純子
■病 床 数/471床
■職 員 数/1529名
ハビリテーション 科、歯科口腔外科、心療内科、耳鼻いんこう科、眼科、心臓血管外科、小児外科、リウマチ科、精神科、神経内科、皮膚科
■看護配置/7 : 1
■認定看護師/救急看護1名、皮膚・排泄ケア1名、がん性疼痛看護1名
■主な設備/ヘリポート、ガンマナイフ、MRI、CT、人工透析72台、ESWL、ICU・CCU10室、電子カルテシステム、320列ADCT、ポジトロン断層撮影センター(PET)、がん集学治療センター、シミュレーションセンター
■関連施設/健康センター、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所
■交通案内/JR中央線「松本駅」より徒歩15分

▲松本保健医療圏約42万人
の中心的存在
▲救急患者さんをヘリで搬送
▲職員専用保育所
「Aiすくすく」
▲松本の夏の一大イベント
「松本ぼんぼん」
週1回、褥瘡対策チームが全病棟を回る活動を支えるものは?

- 皮膚・排泄ケア認定看護師 若林あずささん

皮膚・排泄ケアの認定看護師を目指したきっかけを教えてください。(Median編集部)
- 若林

皮膚・排泄ケア認定看護師
若林あずさ
外科に勤務して3年目に、生活面で不安や不便を感じている患者さんを看て、もっと私に専門知識があったら安心して自宅に帰っていただけるのにと感じたことがきっかけです。特に皮膚の健康を保つことや排泄のケアというのは、人間の基本的欲求を満たすことですから、ケアすることで患者さんの精神的なストレスも取り除くことができます。治療の経過の中でできてしまう傷や生活習慣が変わることに対して、患者さんに後悔してもらいたくなかったのです。その後病棟長との面談で、自分のキャリアプランを話したら、院外の講習会参加へも協力してもらえました。認定看護師の資格を取るための半年間の研修費用も病院から全額支給です。恵まれていますよね。

資格を取ったことによって、仕事に対する思いやケアの仕方に
変化はありましたか?
- 若林

ストーマを造設した患者さんに対して
入院から退院後まであらゆる相談に
のっている
自分の話す内容に自信を持てたことが一番大きいですね。取る前は、患者さんから何か聞かれても自分の知っている範囲でお答えするのが精一杯でした。今は患者さんの立場になって、院内での治療だけでなく、退院後の生活のことまで想定しながらお話できるようになりました。ずいぶん視野が広がったと思います。今なら、ストーマケアの最中に患者さんから「臭いのにごめんね」と言われても、「ガスが臭いのは大腸が活発に動いているからだから、気にしないでください」と。患者さんが臭いに対して、少しでも前向きに受けとめられるように支援できればと思っています。

今の所属部署はどちらになるのですか?
- 若林

院内でのカンファレンス風景。
まず興味をもってもらえるように
丁寧に説明する
私は看護部所属で、数ある病棟を横断して皮膚・排泄のケアができる立場で動いています。各部署・病棟から褥瘡ケアやストーマ造設についての依頼が来れば、その都度出向いて相談にのったり、ケアに立ち会ったりしています。それと1週間に1回、毎週水曜日はストーマ外来を担当しています。当院でストーマ造設をして退院・転院された方を中心に、1日に6?10人、外科の先生と一緒にみています。ストーマは生涯着け続けなければならないので、長いおつきあいになります。院内のスタッフに対してストーマについて知ってもらうための勉強会を開催したり、スキントラブルの最新情報を伝えたりすることもフリーで動ける立場だから柔軟に実践できて、助かっています。
私以外の認定看護師、例えばがん性疼痛看護の市堀美香さんは、関わりの深い『がん集学治療センター』に所属しているので、同じ認定看護師と言ってもそれぞれの専門性が活かしやすい配属になっています。

院内には褥瘡対策チームがあると聞いたのですが。
- 若林

和気あいあいとした雰囲気の中から
患者さんへの最善のケアが生まれる
はい、メンバーは、医師、栄養士、薬剤師、理学療法士、ME、医療事務、看護師の総勢13名です。まさしくチーム医療という人員構成。そのチームで1週間に3回カンファレンスを開いて、実際に褥瘡ができてしまった患者さんだけでなく、予防を必要とする患者さんの相談にものって……。1週間に1回は全病棟を回るようにしています。認定看護師の資格を取ったことで、外部の方とお話しする機会も増えたのですが、うちのように週3回も褥瘡対策チームが活動している病院は少ないようです。それに予防を目的とする患者さんへのケアができていることに対しては、珍しがられます。なかなかそこまでのケアに手が回らないというのが、今の急性期病院の実態かもしれません。

実際に病棟へも足を運ぶと思うのですが、病棟の皆さんの反応は?
- 若林
- 最近では高齢の患者さんが多いので、栄養状態がよくなくてスキンケアが必要な方や、オムツを使用している方のスキントラブルへの対応など気になる病棟へは何度も足を運んでいます。褥瘡チームにいる専門的な知識を持ったメンバーの意見を集約してケアにあたるので、見る見るうちに回復していきますよ。褥瘡は非常に目に見えやすいですし、病棟の看護師にも興味・関心をもってもらえます。私たちの活動が病棟で受け入れられているという手応えを感じられるからこそ、これだけ活動が続いているのだと思います。病棟には週に何度も顔を出すので、「また来た!」と思われているかも知れませんね(笑)。でも一緒にケアしていく中で、治っていく過程を共に喜び合える雰囲気があるのが当院の良さでもあります。お互いにモチベーションを高めながら、患者さんにとって最善の策に取り組むのがチーム医療の使命ですから。そのチカラを最大限に引き出すには、メンバー間の信頼関係とコミュニケーションが大切です。私が橋渡し役になれればいいかなと思っています。

チーム医療と言っても、そのチームを編成して機能させることが大変で、その点、相澤病院のチームワークはいかがですか?
- 若林
- 一つの病院にいると、なかなか院内のことってわからないのですが、当院には、柔軟性と行動力があると思います。理事長はよく「患者さんにとっていいと思ったことはすぐやろう。必要なことをすぐやらなくていつやるの?」と言っています。以前、看護部長に褥瘡カンファレンスをそれぞれの病棟で実施したいと提案したら、「それはいいこと。来週からやりましょう!そのために病棟が困らないように準備しておいて」と即行動に移してくれました。こちらが戸惑うくらい院内の各部署に話が通るのが早いんです。また協力体制もいいから、提案がどんどん形になっていく。そんなやる気のあるスタッフが多いと思います。
それはバンクーバーオリンピックでの応援の時にも感じたことです。スピードスケートの日本代表として小平さんが競技する日の早朝から、みんなその日も仕事があるのに、病院に集まって一丸となって応援していましたからね。相澤病院って「いいな!」と純粋に思いました。あいにく私は学会で東京にいたので、ホテルのテレビの前で興奮しながら、声援を送っていました。今もまだ院内にその時の応援メッセージを書いたポスターが貼ってあるのですが、いい思い出です。


バンクーバーまで応援に
出かけた病院スタッフたち

チームパシュートでの銀メダル獲得は、
このたくさんの応援に支えられていた

今後やりたいことや若林さん自身の将来像を教えてください。
- 若林

いつか看護相談室で若林さんに
会える日が楽しみだ
看護の専門性を活かして、『看護相談窓口』みたいなものを病院内に作れればいいですね。病院って独特の雰囲気があって、患者さんはちょっとわからないこと、聞きたいことを誰に話していいかわからず、遠慮しながらいる場所だと思うんです。そうではなくて、必要な時に、必要なことをすぐ聞ける『何でも相談室』のような場所を、看護師中心になって運営できたら、患者さんは不安や疑問を残さずに家に帰れますよね。そのターミナルのような存在になって、一緒に支援していけたら、看護師としてのやりがいに繋がると思います。
私自身の将来像は、患者さん、スタッフなど、誰に対しても話がしやすい雰囲気を持っていたいです。和気あいあいとした雰囲気の中で、聞かれたら答える、頼まれたら動く、でもできることとできないことの区別ははっきりと伝えられる看護師になりたい。医師と看護師、他の医療スタッフと看護師、患者さんと医療スタッフなど、皆さんの中間にいる、そんな存在が理想です。
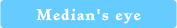
いくら専門性をもった看護師がいても、その能力を発揮できる場所がなければ意味がない。病院という組織は専門職の集団だからこそ、一人ひとりの存在価値がとても大切になる。スタッフそれぞれの専門性を最大限に発揮できる環境があるかどうかが、チーム医療の質を左右する。ここには個人を尊重しながらもチームでより良い医療を提供しようという空気が流れている。資格やシステムを活かすも殺すも、そこで働くスタッフのチームワークにかかっていることを感じた。


















![]()