Pick Up Hospital

NST・緩和ケアチーム・褥瘡委員会・訪問看護etc…さまざまなナースによるさまざまな看護のカタチを徹底レポート!
※掲載されているデータは取材当時のものです
Pick Up Hospital 2 [ 2009.2 ]
ムダなく効果的に行う『依頼型介入』で、質の高い栄養管理を行う。
小川赤十字病院がNST(栄養サポートチーム)の活動を始めたのは2004年6月のこと。職員全体のモチベーションの高さから、現在では活発な取り組みを見せる同院ですが、発足当初は文字通りゼロからのスタート。栄養管理をチーム医療として行うに当たり、同院がどのように考え、工夫し、効果を上げてきたのか、注目してみます。
日本赤十字社 小川赤十字病院
〒355-0397 埼玉県比企郡小川町小川1525
TEL:0493-72-2333(代)内線2315
E-mail:
mail@ogawa.jrc.or.jp
■開 設 年/昭和14年5月27日
■病 院 長/浅野 孝雄
■看護部長/川崎 つま子
■病 床 数/302床(一般252床、精神50床)
■職 員 数/370名
■診療科目/内科、呼吸器科、循環器科、精神科、神経科、外科、消化器科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科(ペインクリニック)、リハビリテーション科
■看護配置/(一般病棟)実質配置 7 : 1 (精神病棟)実質配置 15 : 1
■医療社会事業部/各種検診、人間ドック、脳ドック、訪問看護、訪問リハビリ、災害救護
■交通案内/ (電車)JR八高線・東武東上線「小川町駅」より徒歩15分
(バス)国際十王交通 熊谷駅?小江川?小川町駅線「日赤入口」下車
ときがわ町路線バス 明覚駅?小川町駅線「日赤病院前」下車
NSTコアスタッフに聞く!

- 医師 清水聡さん

- 看護係長
宇田川洋子さん

まずは、NST発足の背景や経緯についてお聞かせください。(Median編集部)
- 清水

NSTの立ち上げメンバーの一人であり、
チームリーダーの清水 聡 医師
活動を開始したのは2004年6月からです。治療と栄養管理は併行して行うことが大切なのですが、以前は必ずしもリンクしているとは言えませんでした。このままでは良くないと言うことで、栄養療法のための勉強会を開催。研究に研究を重ね、院長直属の活動部隊として正式に立ち上がったのが2005年4月です。
- 宇田川
- ドクターや看護師、管理栄養士など多種のメンバーが集まって学んでいくうち、栄養管理・指導を治療と併行して進めることがいかに大切かが手に取るように見えてきました。皆がゼロからのスタートだったことも幸いして、ディスカッションでは遠慮や気後れなどは一切なし。それぞれの専門分野から積極的に参加してくれ、NST活動も活発化していきました。今では、医師3名、看護師約15名、薬剤師1名、管理栄養士3名、放射線技師2名、臨床検査技師2名、事務部1 名が一丸となって活動中です。2007年8月には、院外から3名のNST教育実習生も受け入れました。

勉強会は今でも積極的に行われているとお聞きしたのですが。
- 宇田川

NST学習会のひとコマ。この日は
胃ろうについて知識を深めた
各病棟・外来から担当看護師が参加します。月に一度の勉強会は、年間計画でテーマが企画され、コアスタッフが講師を担当します。3ヵ月に一度の症例発表も臨床のスタッフのモチベーションが高いことが特徴です。また、テーマによっては、外部講師に依頼して講義を行ったりもしています。ある勉強会では、電話回線を利用した、全国同時配信のラインカンファレンスにも参加しました。

NST活動について、貴院が採用している『依頼型介入』とはどのような
ものですか?
- 宇田川

NST教育担当の宇田川 洋子 看護係長
NST専門療法士でもある
『依頼型介入』とは、事前に担当部署でNSTのための準備を行い、その後、介入を行う方法のことです。各部署で働くサブスタッフが、専用用紙に従って簡単なアセスメントを行い、実際の患者さんや社会背景を考慮したうえで、栄養投与量の計算や栄養のアクセスルートなど、さまざまなサポート内容を検討し依頼をかけてきます。NSTのコアスタッフは、それらを基に内容の検討に入り、計画を深め実施するという流れです。これまで、看護師はドクターからの指示を栄養科に伝える橋渡し的な役割が多かったのですが、常に最前線で患者さんと接している私たちがしっかりと事前準備することで、より効率的で自主性のあるシステムになったと思っています。
- 清水
- まさにチーム医療ですよね。計算が難しいとされる栄養アセスメントツールですが、これは独自のソフトを開発し、必要なデータさえ入力すれば誰でも一定の計画が立てられるようシステム化しています。誰が行っても、ある程度の水準に達する計画を作成できることが大切ですからね。

NSTを通して得た成果や、今後の目標について教えてください。
- 宇田川

測定を行い栄養状態の評価を行う
NSTコアスタッフ
この活動をより多くの人に知ってもらおうと懸命にアピールしてきたおかげか、時々、患者さんのご家族から主治医に相談があったりします。また現場の看護師からは、栄養療法の計画が具体的なので介入しやすくなったとの声も聞かれるようになり、活動の効果を実感しています。何より大きいのは、今までなら諦めていたことでも、「もう一度考えてみよう」「もっと工夫してみよう」と、解決の糸口を探る姿勢が身についたことですね。
- 清水
- 同感ですね。職種ごとの垣根もなくなり、有意義な情報交換ができる病院になったと思います。電話一本で用件を済ませるより、顔を見て話す方が良いに決まってますから。今後の予定ですが、最近、超音波による胃排泄能の検査の取り組みを始めました。これは世界でも稀な方法で他からも注目されています。その他には嚥下造影もスタートし、現在50例ほどの実績があります。嚥下訓練をして口からの栄養摂取を促進していきたいと思います。
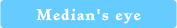
「口から食べ物を摂り、それを栄養として生きていることの重要性を再認識できました」と語る宇田川さん。栄養摂取による自然治癒力を高めるという看護の原点に、一人の看護師としてだけでなく、チーム全体で振り返ることができたのは、大きな成果ではないだろうか。ソフト面はもちろん、日本静脈経腸栄養学会による『栄養サポートチーム専門療法士の実施修練認定教育施設』認定など、ハード面でも充実を見せる同院。今後のさらなる活躍から目が離せない。









![]()