HOME > 東京アカデミー人気講師による国家試験対策講座 > 2月 「精神看護学」
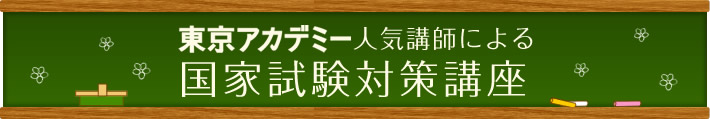
▼前年度分はこちら▼
2月
今月はラストの『精神看護学』です。正答率は比較的高めですが、他の科目と異なり患者の疾患名が提示されず、アセスメントした上での病態を問う問題や、薬物療法の使用法の詳細を問う問題があります。頻出事項には年齢発達に応じた危機状態、防衛機制、精神症状を表す言葉、疾患では統合失調症、うつ、各種神経症障害、器質性精神障害などがあげられます。今回もここは必ず押さえておきたいという箇所をピックアップしました。国試前のチェックにどうぞ活用してください。
問題1
![]()
防衛機制は、それぞれの種類を具体的なイメージができるようにしておきましょう。
![]()
![]()
■ 代表的な防衛機制
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 抑圧 | 有害な感情や欲動、記憶を意識から締め出し、無意識へと閉じ込めること。 |
| 抑制 | 抑圧と似ているが、ストレスが生じる出来事をすぐに取り出せるように潜在意識の中に思考や記憶を溜め込む方法(抑圧は取り出せないように無意識下に溜め込む)。 |
| 逃避 | 空想、病気、自己へ逃げ込む。 |
| 退行 | 不安を緩和する方法として発達段階を逆行する。 |
| 置換え(代理満足) | 不安や欲求の対象をほかに置き換えて満足する。 |
| 昇華 | 満たされない欲求や願望を社会的に受け入れられる行動様式に変化させる。 |
| 反動形成 | 本心と裏腹なことを言ったり、したりする。 |
| 取り入れ 同一視(同一化) |
他人の意見や価値観・考えなどを自分の中に無意識に取り込む。 |
| 投射(投影) | 自分が認めたくない欠点や弱点等を他人が持っていると考える。 |
| 合理化 | 自分の行動、態度に対して他人から非難されないような理由をつける。 |
問題2
![]()
精神症状に関する問題は毎年出題されますが、正答率が低くなるところです。代表的な精神症状は分類に基づいておさえましょう。
![]()
![]()
■ 意志の概念
行動の源となる欲動や欲望を目的、方法、結果に適うように抑制したり、発動させたりする精神作用。■ 意志の異常
問題3
![]()
妄想を持つ患者への対応の原則をおさえましょう。
![]()
1・3・4:×…患者の疑念や不安を軽減し、実際で現実的なことに焦点を当てさせる行動となる。
2:◯…患者の前で、他者と聞こえないように話をする、笑ったりすることは患者の疑念や不安を増強させることになるため、避けるべき行動である。
![]()
■ 妄想
思考内容の障害の一つ。異常な確信に支えられた訂正不能の考えをいう。問題4
![]()
うつ病の昏迷にある状態への援助です。
![]()
うつ病では、疾患の病理により食事に興味が持てず、食事を摂ることができない。そのため、必要に応じた摂食介助が必要となる。場合によっては、食事を口元まで運ぶことも必要となる。
![]()
■ うつ状態でみられる症状
| 感情 | 抑うつ気(日内変動:朝調子が悪い)・絶望感・自信喪失 |
| 思考 | 微小妄想(罪業妄想・貧困妄想・心気妄想…うつの三大妄想)思考制止 |
| 意欲・行動 | 精神運動制止・抑うつ性昏迷・自殺企図(初期と回復期に多い) |
| 身体症状 | 睡眠障害(早朝覚醒・中途覚醒)・易疲労感・食欲不振・体重減少 |
問題5
![]()
パニック発作についての設問です。
![]()
![]()
■ 『パニック発作』診断基準
強い恐怖または不快を感じるはっきりと他と区別できる期間で、その時、以下の症状のうち4つ(またはそれ以上)が突然に発現し、10分以内にその頂点に達する。問題6
![]()
103回に登場したEEについて、おさえましょう。
![]()
EE(expressd emotion)はそのまま訳すと、感情表出である。統合失調症の患者家族のEEが高い(家族が患者に向ける批判や敵意などの感情の動きが高い)場合、患者の再発率が高くなることが、現在の精神医療では知られている。
![]()
■ 心理教育
患者やその家族に、疾患についての知識をわかりやすく伝え、理解を深めることにより、困難に対する対処能力を高めようとするものをいう。家族を対象に行われるものが多い。■ 地域精神医療における家族心理教育
在宅患者のケアをしている者の多くは家族であり、家族の疾病理解や患者に接する家族の姿勢は患者にとって大きな問題である。しかし、家族の重要性に関心が向きだしたのは比較的最近であり、『家族は援助者』という見方をされている。精神科リハビリテーションにおける家族の役割は大きく、家族心理教育は重要である。問題7
![]()
悪性症候群は代表的な抗精神病薬の副作用ですが、『熱が出る』『筋肉が硬直する』『予後が悪い』程度の理解になっていることが多いはず。もう少し踏み込んだ理解をしておきましょう。
![]()
![]()
■ 抗精神病薬
| 薬剤名 | 作用・副作用 | |
|---|---|---|
| 定形抗精神病薬 | フェノチアジン系: クロルプロマジン レボメプロマジン |
鎮静作用が強い。 抗コリン作用、抗α1作用、錐体外路症状が強い。 |
| ブチルフェノン系 ハロペリドール |
鎮静作用は弱いが抗幻覚・妄想作用強い。 抗コリン作用、抗α1作用は弱い。 錐体外路症状が強い。 |
|
| 非定型抗精神病薬 | SDA リスペリドン |
抗精神病効果に優れる。 高プロラクチン血症による乳汁分泌、月経異常、射精不能の副作用。 高容量で錐体外路症状の出現。 |
| MARTA オランザピン |
抗精神病作用、認知機能、うつへの効果。 錐体外路症状、高プロラクチン血症は少ない。 血糖上昇、体重増加がみられる。 |
|
| ドパミン部分作動薬 アリピプラゾール |
マイルドな鎮静効果。 錐体外路症状少ない、不眠、焦燥、胃腸症状がみられる。 |
|
問題8
![]()
精神療法で、よく出題される認知療法の概要、適応をおさえましょう。
![]()
認知のあり方に働きかけて、情緒状態を変化させ問題解決を図ることを目的とした短期の精神療法である。
1:◯…うつ病をはじめ、パニック障害、社会不安障害、心的外傷後ストレス障害、身体表現性障害、適応障害などに効果があるとされている。
2・3・4:×…認知療法の対象となりにくい。
![]()
■ 精神療法
| 種類 | 概要 | 適応疾患 | |
|---|---|---|---|
| 精神分析療法 | フロイトにより創始。心に浮かんだことをそのまま話させる自由連想法を手技とする。患者の示す問題を防御規制から理解し、治療中に患者−治療者間に起こる転移感情等の分析を行う。 | ヒステリー・神経症など | |
| 行 動 療 法 |
脱感作療法 | 学習理論を用いた治療。避けようとする強迫観念や対象に直面させる。 | 強迫性障害 恐怖症など |
| 認知療法 | 情緒・行動の障害を起こす認知の歪みや偏りを患者自身に気づかせ、修正していく治療。 | うつ病・パニック障害・ PTSD・摂食障害など |
|
| 森田療法 | ありのままの不安を受け入れ、不安による悪循環を断つ。入院隔離を原則とし 1期:絶対臥褥期 2期:同じく隔離 3期:作業期 4期:実生活期に向けて治療が進められる。 |
全般性不安障害・ 強迫性障害など |
|
| 自律訓練法 | リラックスした状態で、自律神経系の機能を自己暗示によってコントロールする治療法。疑い深い人には向かない。 | 心身症・自立神経失調症・ 神経症など |
|
| 芸術療法 | 創作的・構成的作業を中心とする療法。 | 統合失調症など | |
| 集団精神療法 | 数人から数十人の患者グループと1人あるいは2人の治療者が円座を作って一定のテーマについて話をする。集団力動を用いた治療。『断酒会』もその一つ。 | アルコール依存症・ 摂食障害・薬物中毒など |
|
| 家族精神療法 | 家族の対人関係プロセスに焦点を当て、直面している問題を自分たちで解決していく方法を家族全体で学ぶ。 | 摂食障害・神経症・境界例 などの他、家庭内暴力や不登校 などにも用いられる。 |
|
問題9
![]()
精神保健福祉法の概要をおさえましょう。
![]()
![]()
■ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要
(平成25年6月13日成立、同6月19日公布)問題10
![]()
精神障害者の社会復帰施策の代表的なものをおさえましょう。
![]()
精神障害者の地域移行・地域定着支援事業は、チェック&チェックを参考。
![]()
■ 障害者総合支援法に基づく相談支援事業(地域移行支援・地域定着支援)
♪メルクリウスの庭♪
国家試験まで残すところあとわずかですね。体調のほうはどうですか。それと寝不足続いていませんか。夜はしっかり休みましょう。All Rights Reserved (C) 2005-2024 Tokyo Academy Shichiken Publishing co,Ltd.